「
家をタダであげます」――もしそんな広告を見つけたら、あなたはどう感じるでしょうか?
「嘘でしょ?」「そんな美味しい話があるの?」と疑う人もいれば、「本当に無料なら欲しい!」と興味を持つ人もいるでしょう。
しかし、日本には本当に
無料で手に入る家が存在します。特に地方では、空き家が増加し続けており、「維持するより手放したい」という理由で、タダで譲るケースが珍しくありません。
一見すると夢のような話ですが、実際には「無料でも貰い手がつかない」ことが多いのが現実です。
では、なぜタダの家があるのに、誰も貰わないのでしょうか?
それには、
修繕費・立地・法的手続き・維持費など、様々な理由があります。
本記事では、「家をタダであげます」となぜ言われるのか、貰い手がつかない理由とその解決策について詳しく解説します。
「無料の家を探している人」も、「家を譲りたいけど貰い手が見つからない人」も、ぜひ最後までお読みください!
無料の家って本当にあるの?
冒頭でも質問を投げかけましたが、「
家をタダであげます」という言葉を聞いて、あなたはどのように感じるでしょうか?
「そんなおいしい話があるの?」と疑う方もいれば、「本当にタダなら欲しい!」と興味を持つ方もいるでしょう。
実際、日本では
無料で譲渡される家が存在します。特に、過疎化が進んだ地域では、空き家を放置すると維持管理費や固定資産税がかかるため、「
誰か住んでくれるならタダでいい」というケースが増えているのです。
なぜ「家をタダであげます」となるのか?
日本には現在、
800万戸以上の空き家があると言われています(総務省の統計より)。その主な理由として、以下のような背景があります。
- 人口減少と過疎化
若者が都市部に移住し、地方の住宅が使われなくなる。
- 相続問題
親から家を相続しても、遠方に住んでいるため管理できない。
- 維持費の負担
住まなくても固定資産税や管理費がかかるため、手放したい。
特に地方では「売りたくても売れない」物件が多く、
タダでもいいから誰か住んでほしいという考えに至るのです。
でも、本当に「タダで家が手に入る」の?
「無料の家」と聞くと、お得に思えますが、実際には
貰い手がつかないケースが多々あります。その理由は単純で、「タダでも負担が大きい」からです。
例えば、以下のような
見えないコストが発生する可能性があります。
| 費用項目 |
発生する可能性 |
参考費用(目安) |
| 修繕・リフォーム費 |
ほぼ必須 |
50万~500万円 |
| 固定資産税 |
住まなくても発生 |
年間5万~15万円 |
| 登記費用 |
名義変更に必要 |
5万~10万円 |
| 解体費用 |
建物を取り壊す場合 |
100万~300万円 |
このように、「タダで貰えるからお得!」と思っても、結局は
修繕費や維持費がかかるため、貰い手が見つからないことが多いのです。
家をタダで提供しても貰い手がつかない理由

家を無料で提供しても、意外と貰い手が見つからないケースが多くあります。その理由は単純に「タダだからお得」という話ではなく、物件の状態や維持費、手続きの煩雑さなど、さまざまな要因が影響しています。ここでは、家をタダでもらうことが難しい主な理由を解説します。
① リフォーム・修繕が必要で費用がかかる
無料の家の多くは
老朽化が進んでいる ため、すぐに住める状態ではありません。特に、以下のような修繕が必要になるケースが多いです。
- シロアリ被害:柱や床が食われており、大規模な補修が必要
- 雨漏り:屋根の損傷が進み、内装にも影響を与えている
- 水回りの故障:キッチンやトイレの設備が古く、交換が必要
これらの修繕には数十万円から数百万円のコストが発生する可能性があります。
修繕費用の目安
| 修繕項目 |
費用の目安 |
| シロアリ駆除 |
約10万〜30万円 |
| 屋根の補修 |
約50万〜150万円 |
| 水回り設備交換 |
約30万〜100万円 |
| フルリフォーム |
約300万〜1000万円 |
「タダの家」でも、修繕費が高額になれば、結果的に購入した方が安い場合もあるのです。
② 立地が悪い(田舎・不便な場所)
無料で提供される家の多くは
都市部ではなく過疎地域にある ため、日常生活の利便性に問題があることが多いです。※都心で立地が良いところは直ぐに売却できてしまう
- スーパーや病院が遠い:最寄りのコンビニまで車で30分以上かかるケースも
- 公共交通機関がない:車が必須で、運転できない人には不便
- 働き口が少ない:移住しても仕事が見つからない
田舎暮らしに憧れる人もいますが、実際には生活の不便さに耐えられず、移住を断念するケースが少なくありません。
③ 維持費(固定資産税・管理費など)がかかる
家は
無料でも維持するためのコスト が発生します。特に、固定資産税や管理費用は住んでいなくても発生するため、「タダでもらったはずの家」が思わぬ負担になることがあります。
維持費の目安
| 項目 |
費用の目安 |
| 固定資産税(田舎の空き家) |
約3万〜10万円/年 |
| 管理費(草刈りや清掃) |
約2万〜5万円/年 |
| 修繕費(最低限の維持) |
約5万〜20万円/年 |
特に、遠方に住んでいて定期的に管理できない場合、雑草の放置や倒壊の危険性が指摘され、近隣住民とのトラブルになることもあります。
④ 法的・相続の問題がある
無料で提供される家の中には
登記が整理されていない ものも多く、受け取るのに手続きが面倒な場合があります。
- 相続登記が未完了:相続人が複数人いる場合、全員の同意が必要
- 土地と建物の所有者が別:土地は借地で、建物のみ譲渡可能なケース
- 抵当権がついている:過去の借金の担保になっており、すぐに売却や移転ができない
家を受け取る前に、登記簿謄本を確認し、法的な問題がないか慎重にチェックする必要があります。
⑤ 近隣トラブルや治安の問題
田舎の空き家などでは、意外な理由で貰い手がつかないケースもあります。
- ご近所付き合いの問題:田舎は地域コミュニティが強く、外部の人を受け入れにくいこともある
- 過去の事件・事故の影響:心理的瑕疵(かし)がある物件(自殺や事件があった家)は避けられる
- 噂や迷信:「幽霊が出る」「昔から不吉な土地」といった理由で住みたがらない人もいる
このような問題は実際に現地を訪れて、近隣住民に話を聞くなど、事前調査をすることである程度回避できます。
「タダの家」と聞くとお得に感じますが、実際には
修繕費・立地・維持費・法的問題・近隣トラブル など、多くのハードルがあるため、簡単には貰い手がつきません。しかし、これらの問題を事前に整理し、適切な対策を講じることで、貰い手を見つけることも可能になります。
次章では、「貰い手を見つけるための対策」について詳しく解説していきます。
貰い手を見つけるための対策

タダで家を提供しようとしても貰い手がつかないのには理由があります。しかし、いくつかの工夫をすれば、スムーズに新しい住人を見つけることが可能です。ここでは具体的な対策について解説します。
修繕費用の一部負担 or リフォーム済みで提供する
無料の家の多くは老朽化しており、そのまま住むには大規模な修繕が必要になる場合があります。しかし、
修繕費を抑えたり、事前にリフォームを施しておくことで、貰い手が見つかりやすくなります。
修繕費負担のパターン
| 方法 |
メリット |
デメリット |
| 一部修繕してから譲渡 |
住みやすくなるので貰い手がつきやすい |
修繕費が発生する |
| 修繕費を一部負担(譲渡後に補助) |
貰い手の負担が軽減される |
一定の費用がかかる |
| リフォーム補助金を活用 |
公的補助を利用できるので負担軽減 |
申請に手間がかかる |
リフォーム補助金の活用方法
無料で提供する家の多くは老朽化しているため、
リフォームをしないと住めないケースが多くあります。その際に役立つのが、
自治体や国が提供するリフォーム補助金制度です。適用できる補助金を活用すれば、修繕費の負担を軽減し、貰い手を見つけやすくなります。
リフォーム補助金の種類
日本国内では、以下のようなリフォーム補助金が利用できます。
| 補助金の種類 |
対象となる工事 |
補助金額 |
| 空き家リフォーム補助金(自治体) |
空き家の改修・耐震補強 |
10万~100万円程度 |
| 長期優良住宅化リフォーム補助金(国) |
バリアフリー改修・断熱リフォーム |
最大100万円 |
| 住宅耐震改修補助金(自治体) |
耐震診断・耐震補強 |
30万~200万円 |
| ZEH(ゼロエネルギーハウス)補助金 |
太陽光発電・断熱強化 |
最大100万円 |
※補助金額は自治体や制度によって異なるため、事前に確認が必要。
どのように申請するのか?
リフォーム補助金を受けるには、
いくつかのステップを踏む必要があります。
- 対象の補助金を調べる
- 住んでいる自治体の公式サイトで「空き家リフォーム補助金」などの制度を確認
- 国の補助金については「国土交通省」や「環境省」の公式サイトをチェック
- 事前相談・申請書類の準備
- 役所や補助金の窓口に相談し、申請条件を確認
- 必要書類(登記簿謄本、見積書、工事計画書など)を準備
- 見積もりと施工業者の選定
- 自治体の補助対象となる業者を選ぶ必要があるケースが多い
- 施工会社に見積もりを依頼し、申請書類を整える
- 申請・審査
- 役所や関係機関に申請を行い、審査を受ける(審査には数週間~数ヶ月かかることも)
- 審査後、補助金が交付される場合は通知が届く
- 工事の実施と報告
- 補助金が認められたら、実際にリフォームを実施
- 工事完了後に報告書を提出し、最終的な補助金を受け取る
補助金を活用する際の注意点
リフォーム補助金を活用する際には、以下のポイントに注意してください。
- 補助金の予算枠が限られている
→ 申請が多いと早めに締め切られることがあるので、早めに手続きを進めるのが重要。
- 工事前に申請しないと適用されない場合が多い
→ すでに工事を開始してしまうと補助対象外になる可能性があるため、事前申請が必須。
- リフォーム業者は自治体の登録業者に限定されることがある
→ 指定業者リストを確認し、対象となる業者を選ぶ必要がある。
まとめ
リフォーム補助金を活用すれば、
修繕費の負担を大幅に軽減できるため、貰い手を見つけやすくなります。ただし、
事前申請や書類準備が必要なため、早めに調査・手続きを進めることが重要です。
タダで家を譲る場合は、
補助金を活用できることを事前に調べ、貰い手に情報提供することで、譲渡の成功率を高めることができます。
立地のデメリットをカバーする情報を提供する
田舎や交通の便が悪い地域では、どうしても貰い手が見つかりにくくなります。しかし、
立地の悪さを補う魅力的なポイントを提示することで、新しい視点での需要を引き出せます。
立地のデメリットを補う工夫
- テレワーク向けの家としてアピール
- インターネット環境を整備し、リモートワーカー向けにする
- 二拠点生活(デュアルライフ)の提案
- 週末や長期休暇に利用するセカンドハウスとしての活用
- 地域の魅力を発信
- 例えば「自然豊か」「のどかな環境」「移住者向け支援が充実」など
無料だけでなく「維持費を抑える工夫」を提案
タダで家をもらえても、その後の維持費(固定資産税・管理費・光熱費など)が高額になると貰い手は現れにくくなります。そのため、
維持費を抑える方法を提示することが大切です。
維持費を抑えるための工夫
| 項目 |
方法 |
効果 |
| 固定資産税 |
小規模宅地や古家減免制度を活用 |
税金を軽減できる |
| 光熱費 |
太陽光発電や井戸水の活用 |
ランニングコストを抑えられる |
| 管理費 |
近隣住民と協力して管理 |
維持コストを分散できる |
相続や法的問題をクリアにする
タダで家をもらう際、
登記手続きや法的な問題がネックになることがあります。こうしたハードルを事前に取り除くことで、スムーズに貰い手を見つけることが可能です。
解決策
- 事前に司法書士に相談し、スムーズに譲渡できる状態にする
- 所有権移転登記を済ませておく
- 相続の問題がある場合は、遺産分割協議書を作成しておく
地域のサポート体制をアピールする
地域によっては、空き家を活用するための移住支援や補助制度を用意しているところもあります。こうしたサポートを活用することで、貰い手が見つかりやすくなります。
具体的なサポート例
- 自治体の移住促進補助金
- 地域おこし協力隊の活用
- 地域の空き家を活用してビジネスをしたい人向けの支援制度
- 地域コミュニティとのつながり
- 新しく移住する人が馴染みやすいように、地元の人と協力する
宮城県七ヶ宿町の移住促進補助金
宮城県七ヶ宿町では、移住者に対して手厚い住宅支援を行っています。特に、20年間住み続けることで土地と建物が無償で譲渡される「地域担い手づくり支援住宅」制度があります。この制度では、新築の設計段階から打ち合わせに参加でき、間取りを自由に決められる点が大きな魅力です。また、新築住宅や空き家リフォームへの補助もあり、新築や二世帯住宅への改修には上限300万円の補助金が支給されます。
宮城県七ヶ宿町移住・定住総合ポータルサイト
石川県志賀町の移住促進補助金
石川県志賀町では、移住者・定住者向けに以下の奨励金・助成金を支給しています。
- 移住定住促進住まいづくり奨励金:志賀町に移住して家を建てる場合、最大200万円の奨励金が支給されます。
- 移住定住促進賃貸住宅家賃助成金:町内に移住して賃貸住宅を借りる場合、家賃補助として助成金が支給されます。
- 移住定住促進空家リフォーム再生等助成金:空き家を購入・リフォームする際、その費用に対して助成金が支給されます。
これらの支援策により、志賀町は移住者の定住を積極的にサポートしています。
しかまちぐらし
タダの家が貰われない理由の多くは、
修繕費・立地・維持費・法的問題にあります。しかし、これらを事前に対策し、
魅力的なポイントをアピールすることで貰い手を見つけることは可能です。
もし「無料で家を提供したい」と考えているなら、
単にタダで譲るのではなく、住みやすい環境を整え、魅力をしっかり伝えることが大切です!
また「無料で家を提供してほしい」と考えているならば、その地域の補助金の情報を取得するようにしましょう!
まとめ
「家をタダであげます」と聞くと、一見お得に思えますが、実際には貰い手がつかないケースが多いのが現実です。本記事では、その理由と解決策を詳しく解説しました。ここで、重要なポイントを振り返りましょう。
タダの家が貰われない主な理由
家が無料でも貰い手が見つからない主な原因には、以下のようなものがありました。
| 理由 |
詳細 |
| 修繕費用が高額 |
無料でもリフォームが必要で、多額の費用がかかる |
| 立地が悪い |
交通や買い物の便が悪く、定住が難しい |
| 維持費がかかる |
固定資産税や管理費が発生し、長期的な負担がある |
| 法的・相続問題 |
権利関係が複雑で、スムーズな譲渡が難しい |
| 地域の環境やトラブル |
近隣トラブルや治安の問題がある場合、敬遠されやすい |
貰い手を見つけるための対策
しかし、これらの問題は工夫次第で解決できます。具体的には、次のような対策が考えられます。
- 修繕負担を軽減する
- 最低限のリフォームを行い、すぐ住める状態にする
- 自治体の補助金やリフォーム助成制度を活用する
- 立地のデメリットを補う
- テレワーク向けや二拠点生活に適しているとアピール
- 地域の魅力や自治体の移住支援策を紹介する
- 維持費の負担を軽くする
- 固定資産税の安いエリアであることを伝える
- 地域の空き家バンク制度を活用する
- 法的手続きを明確にする
- 登記や相続関係を整理し、スムーズに譲渡できるようにする
- 司法書士や専門家に相談し、必要な手続きを事前に進める
- 地域との関係を良好にする
- 近隣住民との関係性を築き、新しい住人を受け入れやすい環境を作る
- 地域コミュニティへの参加を促す
タダの家を探している人へのアドバイス
もし「タダの家を探している」場合は、
表面的な無料の魅力に飛びつかず、デメリットをしっかり理解した上で慎重に選ぶことが重要です。
- 取得後にかかるリフォーム費用や維持費を事前に試算する
- 物件の法的リスク(登記、権利関係)を確認する
- 立地条件をチェックし、生活に支障がないかを見極める
こうした点をクリアにしたうえで、「本当に住める家なのか?」を見極めることが大切です。
タダでも貰われない家には、必ず何らかの理由があります。しかし、適切な対策を講じることで、貰い手を見つけることは可能です。
また、無料で家を探している人も、慎重に物件を選び、事前にリスクを把握すれば、お得にマイホームを手に入れるチャンスがあるかもしれません。
無料だからこそ、よく調べ、よく考えて行動することが重要です!



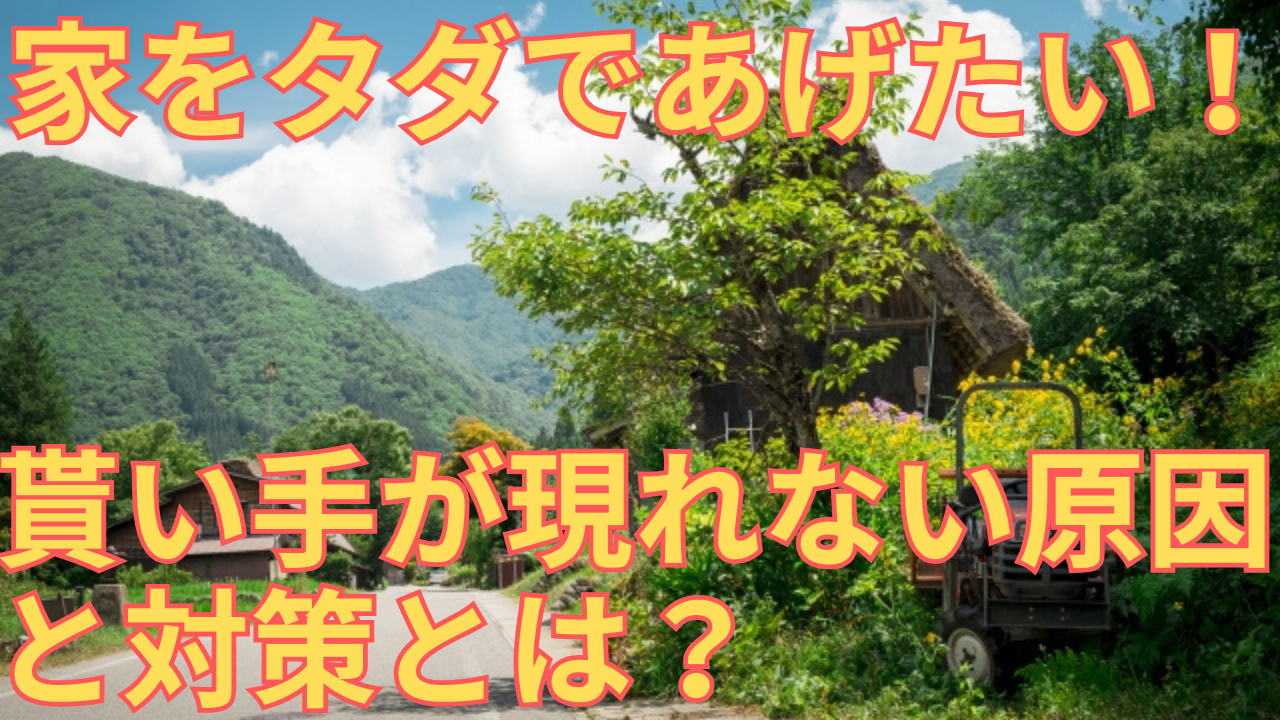
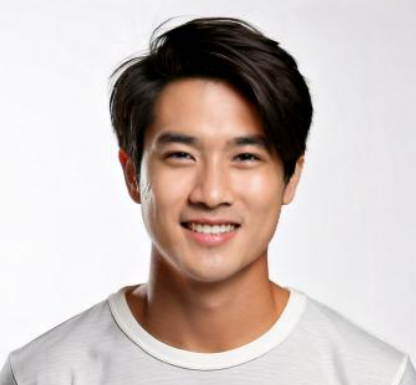



コメント